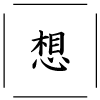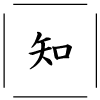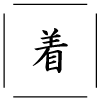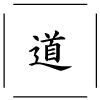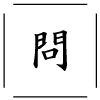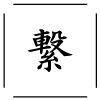なごみ通信 第66号
伝統的な江戸小紋に新しい感性を加えた着物は、胸に強く残って、離れない
大きなマンション、所せましと立ち並ぶ住宅。シャッターの閉まった商店と、オレンジ色の屋根のパン屋さん。
東京・板橋区の住宅街は、懐かしさと新しさが共存する街です。その街のなかに、なに食わぬ顔をして、東京染小紋の工房がまぎれています。人知れぬ工房の主人は、伝統工芸士・岩下江美佳さん。とびきり華やかで、女性の心をくすぐる作品を生み出しています。
万華鏡のように繊細なピンクの花柄、爽やかなブルーのレース柄…。伝統的な江戸小紋に新しい感性を加えた着物は、胸に強く残って、離れることがありません。格式ある江戸小紋が、女性のためのお洒落着に変貌した喜びが、ほんのりとした温もりを持って、いつまでも体に残ります。
江戸小紋は、武士の鎧や最礼装の裃に用いられており、まさに男性社会の象徴です。時代が下り、女性も身にまとうようになった今でも、職人の世界に女性の手は多くありません。そんな世界で、初めての女性伝統工芸士として活躍するのが、岩下さんです。
職人として続けてこられたのは、型染めに対する言いようもない愛情があったから
女性職人としての道は、やはり厳しいものでした。型染めに欠かせない長い板場は、反物を貼って糊を置くことで50kgにもなります。それを一人で頭上まで持ち上げることは、一人前の職人として当然のことでした。そして、毎日毎日繰り返す中腰の作業、型紙や糊のために空調も使わない真夏や真冬。寒さをしのぐために、体がしびれるほど着込むこともあるそうです。
辛さを感じる一方で、職人として続けてこられたのは、型染めに対する言いようもない愛情があったと言います。
「辞めようかなと思うこともありましたが、『あ。だめだめだめ、戻ってきて』と思う自分がいたんです」
離れては生きていけない。シンプルだけれども芯の強さを感じる言葉が、岩下さんの口からほろりとこぼれた瞬間でした。
型染めで一番ときめく瞬間は、初めての型を使うとき
型染めで着物を染めること。それが、岩下さんが惹かれてやまない生業だそうです。東京江戸小紋に欠かせない道具の一つが伊勢型紙ですが、それ自身が伝統工芸品でもあります。小さな点が規則正しく並び、髪の毛一つほどの乱れが最終的に着物の柄としての狂いになるという、想像を絶する緊張感を持つ仕事です。その型紙と丁寧に付き合いながら、岩下さんは柄や色を選び、糊を伏せていきます。
糊伏せの最中、型とヘラがこすれる独特の音が、一定のリズムで続きます。糊を均一に乗せるため、そして余ることのないように、ときどき不規則に端をなぞる音すらも心地よく、訓練に訓練を重ねた所作であることが伝わってきます。
型染めで一番ときめく瞬間は、初めての型を使うときだそうです。糊伏せが終わり、反物から型を離す瞬間。柄がどんな表情を見せてくれるのか、そしてそれをどんな色に染めたら、どんな人が着てくれるだろうか…。きっと、岩下さんにとってその瞬間は、憧れのお店に初めて足を踏み入れるような、少しの不安と甘い予感が合わさった心地なのだろうと思います。
道具すら愛おしむ女性伝統工芸士
「花柄やレースの柄は、自分ではあまり身につけない柄です。けれども着物なら着られちゃう。魔法みたいですよね」
岩下さん自身も大の着物好き。男性社会で生き抜く強さと、おしゃれを楽しむ可憐さを併せ持っています。
女性には、たくさんのゆれる時期があります。女性のゆらぎも、芯の強さも、着物を着ることも染めることも、道具すら愛おしむ女性伝統工芸士。その作品が華やかさと優しさを内包しているのは、同じ女性へのメッセージなのかもしれません。