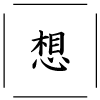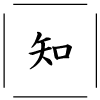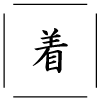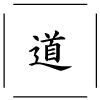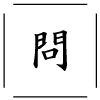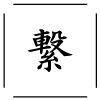なごみ通信 第77号
着物の意匠が持つ古来の価値や意味を大切に
京友禅の世界には、染匠という職業があります。分業制が主流の京友禅では、工程ごとに専属の職人がいます。その数、約20。一反の着物を作り上げるにあたり、それぞれの職人と細やかな意思疎通を図らなければなりません。「染めの匠」と書くその職業は、消費者と職人の仲介役、そして職人同士の橋渡しも行う、ディレクターの役割を果たしています。
京都「染匠市川」さんは、なかでも一流の職人を抱える染匠です。琳派の意匠を得手とする市川さんですが、重厚感のある柄付けばかりでなく、現代のライフスタイルに合わせた軽やかな附下げも手がけています。古典的な柄を現代風にアレンジした作品は、着用シーンを様々に思い描けるほど上品な仕上がりです。
資料室には大量の本や図案のストックが並んでいました。何十年の昔の柄からヒントを得て、配色や柄付けを変えなら、現代社会に馴染む着物を考案するそうです。市川さんの作る着物や帯が、澄んだ美しさを放つのは、着物の意匠が持つ古来の価値や意味を大切にしているからだと気付かされます。
職人同士の橋渡し役の苦労
「京友禅」と一口に言っても、実際に友禅染めを行う工程はほんのわずか。ほとんどは、友禅染めを施す為の下準備と、染めを定着させ反物を整える作業です。
企画から始まり、下絵の作成、草稿紙と言う着物の形をした紙に図案を描き、柄が決定したところで反物に下描きをしていきます。その後、染料が隣り合った柄に染み込まないよう、糸目糊を置いて境を作ります。やっと友禅染を施し、地染めを行い、その染料を定着させるため蒸しにかけます。その後、糊を水で洗い落とし、湯のしで絹本来の状態に戻します。最後に金箔や刺繍で仕上げをするという、膨大な作業量です。
一反に関わる人の数を考えると、職人同士の橋渡し役の苦労が忍ばれます。
着物を着る人の好みが十人十色であるように、職人も十人十色
どれひとつとして欠かすことのできない工程。しかし、職人不足の波は、京都にも押し寄せています。華やかな京友禅の世界ですが、業界が抱えている課題は、やはり職人の維持と、技術の継承です。
「染匠市川」三代目・市川昌史さんは、自ら新しい作品を生み出すことで、職人が技術を発揮する機会を作っていかなければと考えています。
昔は問屋からの発注を受けて白生地を受け取り、制作に取り掛かり、完成した商品は全て問屋が買い取るという流れが主流でした。現在では工房で商品の開発・制作・販売を一手に担うところも増えてきています。注文を受けた商品をひたむきに作ってきた時代から、消費者が喜ぶものを自分たちで考えて作る時代へと変化したのです。
そのため、長く得意としてきた琳派の意匠ばかりではなく、現代的でシンプルな着物や帯も手がけるようになりました。「着物を着る人の好みが十人十色であるように、職人も十人十色」と市川さんは言います。幾何学模様を描くのが得意な職人、草花文様が得意な職人、流水文様が得意な職人…。それぞれに個性と、必要とされる技術があります。生み出す着物が、あるテイストに特化してしまうと、そこに該当する職人にしか仕事が回らず、結果的に技術が廃れることを懸念し、あえて多種多様な作品を手がけているのです。
しかし、この方針の変換には、大変な苦労がありました。職人の考える「美しい着物」と、着る女性が感じる「美しい着物」の感覚には乖離があったのです。冠婚葬祭を大々的に行っていた時には、柄付けが多く、華やかで重厚感のある着物が似合いました。冠婚葬祭が簡素化した現代には、当時の着物は存在感がありすぎ、よりシンプルで場に溶け込むものが好まれます。
伝統と斬新さの組み合わせの妙
その感覚の差を埋めるべく、実際に着物を着る女性の立場を代弁できる人が製造卸問屋の代表の立場にある糸川淑美さんでした。長きに渡り京都室町のしきたりであった男性主体の問屋業界の殻を破って台頭、眼力のある頼もしい女性です。市川さんの高い技術を頼ってこれからの女性が「着たい」と思う着物の制作を依頼しています。
柄の数を減らす、大きさを変える、地色を変える。古典柄を今様に意匠化、それらの組み合わせを変えることで、伝統の説得力はそのままに、時代に沿った着物へと昇華するのです。
伝統と斬新さの組み合わせの妙。市川さんと糸川さんが手がける着物から、清らかな美しさを感じるのは、過去と現在の両方を尊重しながら、未来へ向けてものづくりに取り組む姿勢が現れているのかもしれません。