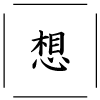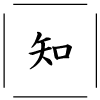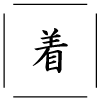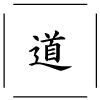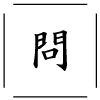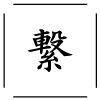なごみ通信 第71号
「幻の花」と言われていた紅花に魅せられて
絹織物の里、山形県米沢市。紬にお召しに草木染め…。雪深いこの土地では、多様な絹織物が生まれています。
そこで紅花染めを営む「よねざわ新田」さんは、130年以上続く機屋のひとつ。もとは武士の家系ということもあってか得意は袴地で、「米沢袴地といえば新田」と言われ続けてきました。現在でも、五代目源太郎さんは自由な発想の袴地を作り続けています。
そんな新田家の転機は、三代目秀次・富子夫妻が紅花と出会った明治38年。当時「幻の花」と言われていた紅花に魅せられ、その復興に着手したことでした。
「紅」に惹かれる人の心は止められない
江戸時代には、「最上紅花、阿波の藍玉」と言われるほどに盛んな産業だったといいます。そんな中にあっても、紅花から採れる紅はとても貴重なもので、金と並びたてられるほど高価なものでした。
明治に入ると、輸入染料や化学染料に取って代わられ、急激に衰退。明治10年頃には壊滅状態だったと言います。
しかし、「紅」に惹かれる人の心は止められません。紅花染めの艶やかな韓紅、化粧に紅を用いたときの、顔に馴染む薄紅色。三代目ご夫妻も「紅」に魅了され、文献の研究から染めの試行錯誤など、たゆまぬ努力の末に、今の新田家を築き上げました。
繰り返すことで深みが増すということ
7月の緑輝く季節。朝露残る早朝から、ひとつひとつ花弁を手で摘み取り、水洗いして黄色の染料を流してしまう。2・3日自然発酵させて赤みを出し、煎餅状に小さく平たくして乾燥させ、保存する。その「花餅」に藁灰の上わ水、烏梅、米酢を加えて赤色を発色させ染める。
保存から染色までの一切を、化学薬品などを用いずに、天候と相談しながら行っています。「昔ながら」という手法が、自然と付き合っていくうえで、最も理に適っていることに行き着いたのだと思います。
そんな新田家の居間には、「新田家行事一覧表」が掲げられています。1月1日にはお餅、納豆、あずきにお雑煮。4月2日は草餅を食べる。5月15日には酒を飲み歌を唄って休む…。
源太郎さんのおばあさまが書き記した行事一覧に則って、今も暮らしています。簡素にした部分もあるそうですが、先達の教えに従うことが、時節に沿い、豊かな生活の助けになると知っているようです。
「100年続いた古い家業を背負うことは、大変といえば大変だけど、そういうもんだと思えばそれきり。夏になると半袖を着て、寒くなってくれば自然に厚着をするみたいに、受け入れるだけです」と、源太郎さんは語ります。「伝統」というものが当たり前に身近に存在していた源太郎さんにとって、続けていくことは稀なことではないようでした。
一度の染色で白色が桜色に、回を重ねれば紅色へ。繰り返すことで深みが増すということが、心身に染み渡っている人の大器を感じました。
「紅」を作る神様との橋渡し役
魔除けの色とも言われ、神秘的な美しさを持つ「あか」。その色は、私たちの命を繋ぐ色でもあります。「あか」に願いを込め、お宮参りや七五三、婚礼や還暦といった儀礼には、必ず身につけてきました。お赤飯、水引、口紅など、形は違えど、平穏無事の祈りが神様に届くようにと、少しの「あか」を用います。
そんな神聖な「紅を」作る新田さんは、神様との橋渡し役とも言えそうです。